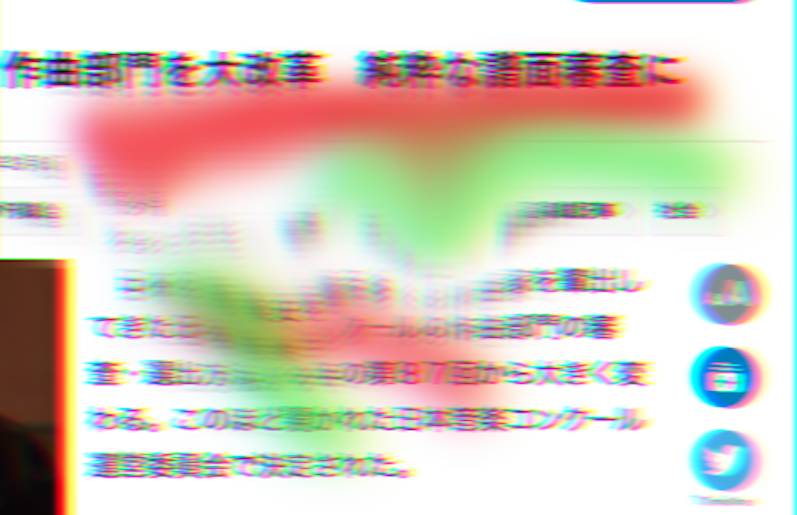「純粋な譜面審査」とは?
「Unity Capsule」への序章」
権威ある日本音楽コンクールの作曲部門が、本選会での演奏審査をしないことに決め、その理由として、より「純粋な譜面審査」をするため、という言葉が使われて物議を醸したのがだいたいおととしの今頃だった。
客観的に見て予算の問題でそうなったのは明らかだったにも関わらず、審査委員長の公式な見解として(建前にせよ)「演奏家たちによる実演は、譜面の厳密性を削いで、人間的なバイアスをかけてしまう」というようなコメントが出されたから、それが音楽家たちの神経を逆撫でして火に油を注いだ、というような一連の出来事だったと思う。
現在でも譜面審査のみで作曲のコンクールが行われているとしたら憂慮すべきことだが、それはまた別の話とする。
自分としてはこの騒ぎで「楽譜」というものの、特にクラシック-現代音楽に対する、人によって微妙に見解を異にするその温度差などを含めた位置付けや存在感が浮き彫りになった、ということを実に興味深く感じたものだった。
「楽譜通りに演奏する」というのが西洋クラシック音楽の大前提であり、「楽器が出来る」というのは常に「楽譜の読み方を知っている」ということとセットでないと認められないことになっている。
楽譜をある程度「即座」に、ある程度「深く」読める、「ソルフェージュ」と呼ばれる反射運動的な能力を共有していれば、作曲家は自分の意図を演奏者にすぐに伝えることが出来るし、知らない人間同士でもアンサンブルが出来て短時間で音楽を成立させられる、という意味では「楽譜」は強力な道具である。
その一方でクラシック音楽においては、すべてが楽譜に書かれているわけではないから「作曲された背景を知る」ということがレベルの高い解釈につながる、ということになってきもする。
「当たり前すぎることは書かれない」としたら、「楽譜通りに演奏する」ことでロボットのような演奏が生まれてしまうことを防ぐために、時代と地域に基づくローカルな背景の検証で演奏を補完することが必要になる、というのは「音楽」と「楽譜」をめぐる、矛盾めいた面白い文化である。
また、クラシック以外の音楽においては、ほぼ例外なく「即興演奏」が使われることも思い出しておきたい。インド古典音楽しかり、フラメンコしかり、ジャズしかりetc..
「即興」が前提になっていれば、演奏に生き生きとした表情や闊達さを与えるためのハードルはぐっと低くなる。こう考えるとひたすら「楽譜どおり」に演奏されるような音楽が、実は世界的に見れば例外的であるのがわかってくる。
そこで「クラシック音楽」の最高学府にして代表的な見解の表明者ともいえるパリコンセルヴァトワールは、いち早く「即興演奏」の授業を取り入れる。
即興演奏の経験を経た後に「楽譜どおり」の世界へ戻ってくることで、より高度な演奏感覚を獲得できるかもしれない。
闊達さの欠如を埋めるため、教育課程の中へ「体験的に」即興演奏を取り入れているとしたら、これもまたなんという矛盾でアクロバチックなやり方だろうか。
このようなことは、数多ある例のほんの一部であり、クラシック音楽をグローバルに広めるために「楽譜通りに演奏すればよい」という、一見わかりやすい方法を採用した人々は、結局のところ「楽譜」と「音楽」の間に生まれがちな矛盾と齟齬を埋めることに苦心して、ありとあらゆる努力を注ぎ込むことになったんではないだろうか?
文学や美術、演劇などの表現者たちが、「百万言をもってことばにならない気分を表現する」とか「写実性や構築性を捨てて、ドリッピングや筆のいきおいで絵を描いてみる」とか「わかりきった感情をことばではなく、わざわざ踊りで表現する」というようなことをするとき、彼らには「抽象表現に向っている」という強い意識がはたらくと思われる。
かたや音楽家たちが仕事をするとき「抽象表現をしている」というような意識は持ちにくいものである。
この「無自覚さ」は「楽譜に沿って忠実に演奏する」という、訓練された通りのルーティーンがもたらす感覚と思われる。
作曲家たちの仕事ですら、ひらめいた着想を楽譜にしていくのは、まるでレンガを積むような単調さと言えないこともない。
これほどシンプルでわかりきった行為はないのである。
しかし、画家や小説家や俳優たちからしてみれば、それでも「音楽」というのは彼らがやっているどれにもまして、高度に抽象的な表現である。
モーツァルトのソナタであれ、ジョン・ケージの前衛音楽であれ、それが「音」という曖昧なものの組織である以上は。
アカデミックな作曲の世界では「エクリチュール」(書法)という言葉が使われるが、これもまた文学や哲学の世界からの借り物のことばなのであり、音楽行為がもともとは「ブラックボックスに手を突っ込んで、形ならぬものと格闘する」ようなことだったと思い出してみるなら、「楽譜」はそれだけでは「聴きて」に届かないことがはっきりしてくるのではあるまいか。
文字によるエクリチュールは読み手に直接はたらくが、楽譜はそうではないからである。
「「音楽」は「楽譜」という上位の抽象表現を「演奏」に落とし込むことで成立している。西洋音楽の特殊なところは、作曲家が熟考して作った楽譜をプレーヤーたちがありとあらゆる努力を重ね、出来るだけ正確で、精度と質の高い「音」に形づくろうとすることで高い芸術性を持つようになったこと」
というような理解を、普通に注意深い聴きてであれば持っているものである。
そして以上のようなことを踏まえてさらに言わせてもらうと演奏に高い精度を求める、どんなに厳しい作曲家でも、生演奏によるある程度の「誤差」は計算に入れて楽譜を作るものである。
どのくらい、あるいはどのようにそういった「緩衝地帯」あるいは「潤滑油」と言っていいような仕掛けを楽譜の中にもぐり込ませるか、というのが作曲家たちの技倆であり、個性でもある。
言い方を変えれば、作曲家たちはどこまでいっても、プレーヤーの肉体が追い付かないようなことは書けない。
「物理法則を無視することはできない」のである以上は「純粋な譜面の美しさ」だけが独立して存在することはあり得ない。
それはイデア論である。
コンピューターゲームの世界で、小さな子供が巨漢のファイターを吹っ飛ばすような。
あるいは、完璧に純正な三角形を現実に描くことは可能か?
完全に瑕疵のない姿を再現するのはどんな手段を使っても不可能ではないか?
以上のようなくどくどしい言葉を費やしてやっと「譜面の厳密性」なんて言葉にいきり立って反応した、経験ある音楽家たちの肌感覚の何百分の一かが説明できるか出来ないか、といったところである。
少なくともこれが、木ノ脇が「楽譜」と言うキーワードを通して音楽を考えたときのことばで、次回は以上の見解をもとにBrian Ferneyhough「Unity Capsule」 を考えて見たいと思います。